プシコ ナウティカ<第4章>
- 2016.04.06
- 日記
今回はプシコ ナウティカ第4章を読み終えて、忘備録的に感想を残すことにします。詳しい内容は、ぜひ本をご購入いただき、お読みくださることをお願いいたします。

松嶋健「プシコ ナウティカ」世界思想社
第2部 イタリア精神保健のフィールド
第4章 主体性を返還する
精神病院は人間をモノ化するということについて論が進んできましたが、では、人間を人間として扱うとはどういうことなのかについて論じなければなりません。主体性のはく奪で一番わかりやすいのは強制的治療です。一方でイタリアの精神医療改革とは「主体性を返還する」ということで表現されるとしています。精神病院はたとえどんなにきれいで快適であっても、それはやはり強制収容所と同様であると考えられます。そして主体性を返還する前に、私たちはまた問わなければなりません・「主体が主体であるための諸条件とはなんであるか」。
バザーリアは「問題なのは病気なのではなく”危機”である」としました。危機という状況下において必要なものは薬ではなく、主体性を行使しうるような関係性と環境を整えることでしょう。それは「自由」という言葉に表されるかもしれず、それは何かをするための時間、空間、物質的な手段を持つことであるとしています。したがって、長期に入院してきた人が「入院していたい」ということだけで自己決定権を尊重するわけではありません。それは具体的な退院後の生活について現実的な可能性が奪われていればそうせざるを得ないからです。選択の自由が保障されないところには自由や主体性は存在しないということです。
イタリアでは精神病院が解放されてきた時期にも、最初は多くの入院者が「ここにいたい」といっていたそうです。精神病院において制限されていた「自由」が与えられるということが重荷になった人の例が書かれています。私たちの多くはこのケースを読めば心の中になにか居心地の悪さを感じるのではないでしょうか。「自分で何でも決めることのできる自立した主体」とは何なのでしょうか。主体性とは意思や欲望を動機づけ、それを具体的に追及可能なものにすることによってはじめてそれが行使できるようになるのであり、そのための環境を整えることの重要性を感じました。つまり、主体性や自由とは、決してその人が一人きりでなんでも決定しなくてはならないことを意味するのではなく、協働作業として少しずつ実現されていくもののような気がします。
地域精神保健の仕事について重要な3つの言葉は「主人公であること」「自覚」「可能性」とされています。主人公であるということはWRAPでも強く意識されている「人生の主導権を手にする」ことです。「自覚」とは危機へのその人のなりの対処法を自覚することで、さまざまな対処プランにあたるような気がします。「可能性」とはもっといい対処法があることを発見していくことで、「学ぶこと」「サポート」に近いような気がします。
イタリアでは医療制度そのものが改革され、行政が医療保健を平等に国民に提供することになりました。地域精神保健サービスが構築され、精神保健の活動において中心的な役割を果たすのは精神保健センターであり、ここが地域精神保健サービスのかなめになっています。公的精神病院ではないところが重要なのだと思います。
筆者が訪れた地区の精神保健センターはかつて病院院長の邸宅だったところを使用していました。通常このセンターは町中のアクセスのよいところに設けられ、かかりつけ医を通さずの直接来訪も可能になっています。初回面接のことをイタリアではアコグリエンザ(歓待)と呼び、雰囲気作りが重視されています。多職種チームのスタッフは職種を超えてオペラトーレと呼ばれます。毎週リウリオーネという情報共有ミーティングが行われます。それぞれの人の担当チームの責任者には職種は関係なく、その人を最も良く知る人が責任者になります。センターのアプローチ方法は精神科の外来とは異なり、職種による考えの違いがあっても利用者に関する取り組みにおいては協働します。オペラトーレは「状況の責任を負い」「共に道程を歩む」ことによって、その人の「人生の参照点となる」つまり、そばにいて利用者が自分自身の別の可能性がみえるような存在になるのです。参照点とは具体的な場所のことではなくて、人生の航海、魂の航海において、自分がどのあたりにいるかわかるようになるということです。このサポートのあり方は、私たちの思い描く、診断名のあるなしにあっかわらない、ピアサポートの在り方が示されているような気がしました。
わが国では精神科医療の進展を精神科救急やスーパー救急に力を入れる方向性になっていますが、イタリアの方向性はかなり違っています。精神医学的なものを含む評価は一つの評価にすぎず絶対視されません。この本では、引きこもっているある男性の家でのやりとりが詳細に書かれていますが、それは私にとってはアウトリーチ事業で行っていた実践を思い出させ、さらにもっと積極的な関与にも思えました。
イタリアでは現在、「精神疾患」「精神障がい」という言い方はほとんど聞かず、「精神的な不調disturbo mentale」や「居心地の悪さDisagio mentale」を用いているということで、これは私たちの言い回の「精神的困難を経験する」であったり、「居心地の悪さ」はそのものだったりします。そしてそういった状況にある人が主体性を行使するためのベースが居場所ということになります。これは「ハウス」ではなく、サッカーでいうところの「ホーム」に該当しそうです。
グループホームの一つカーサ・ファミリアの住人は「オスピテ」(お客の意)と呼ばれ、あくまで一時的な滞在者という意味もこめられています。カーサ・ファミリアは居住系施設ですが、行動制限などは全くありません。しかしそこでは、共同棟の大広間での食事など、一人でもいられるが「一緒にいること」を学びなおすことが重視されます。このカーサ・ファミリアはというのは、本当の家ではないけれど、居心地が良いとカーサ・ファミリアの生活に適応しきってしまって、外で一人ではやっていけなくなってしまうという弊害もあるようです。街中にあったり、郊外にあったり、かつての精神病院の一部を改装して使っている場合もあります。そして、社会協同組合からオペラート・ソチャーレが来てオピステの日中の世話をしています。私たちの目指す活動の一端に触れる気がしました。そこではオペラートとオピステの間の管理や規則をめぐるコンフリクトも生じるのですが、その体験から、他者と「一緒に」いながら「一人でいる」ことをそれぞれが学ぶのだと記してあります。つまり「一人で自分自身と一緒にいること」がカーサファミリアから出ていくために必要である、ということは、希望の感覚を持つことや居心地の悪さとも一緒にいることができること、何もしないことを楽しむことができるようになること、といえるような気もします。また、喜怒哀楽を感情として表現することもカーサファミリアのように人の間で学ばれるとも指摘しています。
そして自立と依存の弁証法として実践の内容が詳しく論じられています。どれもこれも、わが国の私たちの地域生活支援実践で課題となることばかりで本当にためになります。服薬に関するやり取りの一例が描かれていますが、主体性の範疇は自己決定の範疇より広く、自分の周囲の人も含めた集合的な形で行使されうる、ということに、私はこの部分が非常に心に残りました。限定的な場面においてだけ「自己決定」や「自己責任」の論理が持ち出されることについての注意喚起も同意できるものでした。
さらに「本物の希望」について、希望がないところで自己イメージが拡大することは不健康であるとし、行動の現実的な可能性が希望を生み出すのだと指摘しています。
「一人の人間の生というのは人々のあいだで営まれるものであり、そうした多数の生が、「わたし」を支える、見えない「われわれ」として常に生きているからこそ、私たちは一人で生きていることができるのだし、能動的な〈主体性〉を現実に行使することが可能になるのである。
で、この章は結ばれています。
最後までお読みいただいた方、どうもありがとうございました。
-
前の記事
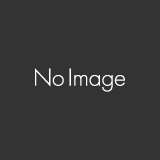
障害者差別解消法が施行されました 2016.04.01
-
次の記事
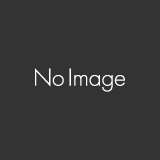
タバコ使用は精神病の原因となるか? 2016.04.08