プシコ ナウティカ<第3章>
- 2016.03.30
- 日記
今回はプシコ ナウティカ第3章を読み終えて、忘備録的に感想を残すことにしました。詳しい内容は、ぜひ本をご購入いただき、お読みくださることをお願いいたします。

松嶋健「プシコ ナウティカ」世界思想社
第2部 イタリア精神保健のフィールド
第3章 病院から出て地域で働く
ここでは著者がイタリアのある地区で行ったフィールドワ-クに基づいて話が進んでいきます。精神病院は人間をモノ化する、という考えがあります。それは隔離拘束だけではなく、個人の持ちものー個人の歴史や記憶に結びついたもの-を取り上げることを通して、「生きている身体」を有する人として扱われなくなるということを述べています。そして「施設化」は患者ばかりではなくそこにいるスタッフにも及んでくると指摘しています。
精神病院を「人間化する」という発想によって、病院では自由が拡大され、病院での集会には地域から人が訪れるようになりました。病院の壁が関係性を遮断する境界ではなく、コミュニケーションと交流が起こる敷居に変化したのです。しかし、古参の看護師の中からは変化への抵抗もありました。そのような人たちは症状の軽い人は地域に出すことができるが、重症の人には入院が必要だというものでした。しかし症状の軽重を判断をするのは医師であり、精神医学が知の名のもとに権力を行使してきたということについてバザーリアたちは問い直すべきとしたのでした。
わが国でも同じことがハンセン氏病の方の療養所と精神病院で行われていました。どちらも社会的な見地から人間をモノのようにしまうことのために設置されたと思われるような施設でした。いま、わが国においてふたつの困難を持つ方々の施設のありようを考えるとき、大きな違いが生じているのはどうしてなのか、私たちも問われているような気がします。
精神科医であるフェデリコ氏の語りにより精神病院における精神科医の抱える不安「私はここで何をしているのだ」についても触れてあります。必要なのは「話を聴くこと」でした。それは相手の病状を評価しながら会話することではなく、人と人として相対することでしかない、ということだったのだとされています。精神科医が精神科診断学という武器を手放して一人の人間としてかかわっていくためには、不確かさや寄る辺なさへの不安に精神科医は耐える必要が生じ、そして自らの孤独を自覚することが新たな可能性を開くとされています。続いて「本人が主人公であること」「多職種チーム」について触れられています。私たちが今とりかかっていることが、イタリアでは50年近く前にすでに取り掛かられていたことに言葉を失います。
「精神医学/精神医療」と「精神保健」は、日本語ではあまり差異が感じられませんが、精神医療では精神科医が専門家であるのに対し、精神保健の専門家は本人とサポートチームの全員であるという考え方の違いがあります。後者の考え方では本人だけが専門家なのではなく、チームの全体が問題解決に取り組むということになります。しかし主人公はあくまでも本人であり、これはWRAPにつながるような気がします。「接し方」のマニュアルはなく、人同士の出会いが可能になるような制度が必要になってくるのだと思います。そして精神病院での改革は結局、精神病院の「人間化」には限界があるということを明確化したのでした。
W県では1968年から精神病院のための看護師コースという専門教育が始まりました、このコースを修めた看護師は病院い配属されましたが、同じ時期から地域に患者さんを戻す運動が開始され、「グルッポ・ファミリア」というも開設されるようになりました。これはわが国のグループホームとは異なり、引き受け手がいない場合に、同じ地域出身の患者同士でグループを作り、地域に戻ったら一緒に共同生活を行うというプロジェクトのことです。入院者は病状ではなく出身地別に編成しなおされ、戻る場所がはっきり意識されました。スタッフも入院者もともに地域に出ていくことが可能になりました。
病院から地域へという流れへの抵抗は、病院内部だけではなく地域にもありました。地域住民とも地域の中での集会を持ち対話を繰り返していきました。それは、精神病を持つ人が地域に戻るということは単に一個人の医療的な問題であるのではなく、地域全体の政治的な課題であるということが病院の内外で共有できていたということなのだとしています。
具体的な地域、という小さな社会での決定のありかたとして、イデオロギーに基づいてなされるというよりも個人の考えや行動を知り、人を単純化されたカテゴリーに分類して考えないでいくことの必要性が説かれており、そのために必要なものは顔であり名前なのだとされています。もう一つは、精神病を持つ人への偏見の問題で、これを乗り越えることについても個人を大雑把に把握できる関係性があることが重要とされます。「一人の人間が他の一人によって具体的に理解されるということ」が<真正性の水準>と呼ばれるものであり、それがイタリアにおける精神医療から精神保健への転換という文脈で起こったことだとしています。もちろん、それは一言で片づけられるような簡単なことではない、となっています。
「じかに話し合う」というのが必要になるのですが、それは生活の場面で繰り返しおこなわれなくてはなりません。まさしくアウトリーチの思想です。治療は外来の診察室にあるのではなく、相手の方の生活空間を知りライフスタイルを知ることから始まり、地域とは「病院の外」の意味ではなく、ともに居場所もしくは生活の場のことなのだとされています。したがって地域とは移行させられる場所ではなく、その人が居場所として生活できるテリトリーなのです。
地域で働き始めた看護師たちは、徐々に病気の症状だと思っていたものが施設に入れられていた人の起こす反応であったことに気がついていきました。そして入院していた人たちが地域で回復することを目の当たりにして、看護師の仕事は喜びを伴うものになったのです。仕事は管理ではなく「同行二人」でした。病院の外で様々なことができるようになったかつての入院者と同じように、病院を出た医師と看護師もまた自らの可能性に驚き喜んだのではないでしょうか。
さまざまな法律を順守することばかりではなく、制度をうまく使ったり、またぎこしたりして活動がなされていったようです。それは精神科医と行政の間の「顔の見える関係」があればこそだったかもしれません。さまざまな関係性を構築していくなかで、一人の人間が他の一人の人間に具体的に理解されること自体が、治療的な過程になっていくのだと法人の訪問看護活動も通じて感じていることが文章になっていて、深くうなずきました。
最後までお読みいただいた方、どうもありがとうございました。
-
前の記事
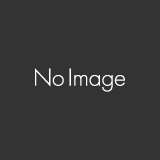
プシコ ナウティカ<第2章> 2016.03.27
-
次の記事
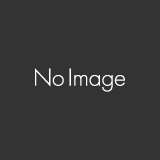
障害者差別解消法が施行されました 2016.04.01