30年目
- 2025.01.17
- 日記
今から30年前の1995年1月17日午前5時46分、阪神・淡路大震災が発生しました。
毎年この日は私にとって大切な1日です。早朝に起きてテレビをつけ、同じ時刻をその当時を思い出しながら迎えています。あの大震災の頃、まだ精神科医歴の浅い私は、大学と勤務先から許可を受けて救援活動に向かいました。そしてその地での経験は、私にとってコミュニティとはなにか、人とは何か、を考えるきっかけとなり、自身の臨床姿勢を方向付ける大きな経験となったできごとでした。
あれから長い長い年月がたちました。自身が定年を迎えるような年齢に至ってからは、日々の暮らしは当たり前に続いていくものではなく、平凡とはありがたいものだと知りました。人との間のつながりと一期一会の大切さを学びました。困難な経験を得た方々から回復するとはどういうものなのかを教わりました。
さまざまな人々と出会いました。今年も、もう二度と会うことのない多くな人々の顔を思い出し、かつての仲間と心の中で対話したいと思います。若いころに一緒に語り合い、熱くさまざまな夢を語りあった大事な人たちとの日々を記憶から呼び起こし、まだ旅の途中である、自分自身の目指すものへの道のりを振り返えります。

http://kobe117shinsai.jp/area/higashinada/a060.php
「こころは傷つく」というごく当たり前のことを精神医学の立場から提唱し、わが国で解離性障害の存在に臨床的な光を当てることに尽力された故・安克昌先生ほかのすぐれた精神保健福祉分野の実践者の方々と出会えたことは私にとっての恵みでした。心の傷つきを持つ人々の回復を支援するためには本当に理解することができなくても「わかろうとする」「聴ききる/対話する」という水平の関係が重要だと教わりました。「支援」という関係性の中での権力性に敏感となり、上下関係を押しつけたり、自身がカリスマの立場にたつことについて慎みを持つべきであると学びました。
私たちの社会は今、おさまらない新型コロナウィルス感染症の脅威になすすべなくさらされ、経済の失速を味わい、戦争による相互の憎しみによって分断され、他者への敬意を失いかけている気がします。今こそ、「愛すること」とはどのようなものであるか、自身に問いかける必要を感じます。
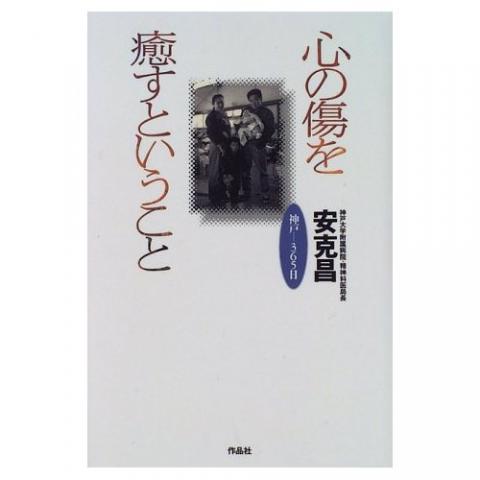
「世界は心的外傷に満ちている。”心の傷を癒すということ”は、精神医学や心理学に任せてすむことではない。それは社会のあり方として、今を生きる私たち全員に問われていることなのである。」安克昌著「心の傷を癒すということ」より
「心的外傷から回復した人に、私は一種崇高ななにかを感じる」と安先生は書かれました。そして、傷ついたそのひとたちを迎え、その回復過程をともにしうる社会こそ、「品格」のある社会だと提唱されました。今日はNHKで放映された「心の傷をいやすということ」のビデオをもう一度視聴しながら、心の底にある軋みをかみしめたいと思います。
最後までお読みいただいた方、どうもありがとうございました。
-
前の記事
新入職員のお知らせ 2025.01.16
-
次の記事
どうすればよかったか? 2025.01.27