DPAT活動@熊本県宇土市で感じたこと
- 2016.05.27
- 日記
熊本県・大分県を中心とした大震災の精神科救援活動DPAT(Disaster Psychiatric Assistant Team)の山梨県班第3班として、弊法人から5名がさる5月5日から5月9日まで、熊本県宇土市で活動を行いました。

安易なこころの支援については、私は個人として阪神・淡路大震災のときの救護所活動の経験から思うところがありましたが、到着した日にテレビで「子どもに地震について積極的に表現してもらうのがよい」という趣旨の放送があり、驚きました。さまざまなところで、災害時の心理的ケアについてのマニュアルも発表されているというのに。(災害グリーフサポートプロジェクトを参照のための一例としてあげておきます)
http://jdgs.jp/4supporter/PFA.html
http://jdgs.jp/4supporter/care4child.html

DPATチームは避難所を回らせていただきましたが、日ごろの診療の視点もあり、アルコールについての意識を持ちつつお話をさせて頂く方もいらっしゃいました。それでも、思うのは、「災害にあった人がみんなトラウマを抱えているわけではない」「災害に会い、人間は成長したり今までに気づかなかった力があったことに気がついたりする」ものだろうと思います。避難所で、会合で、お店で、私たちとお話ししてくださった皆様、本当にありがとうございした。そして、ある避難所で私たちを勇気づけてくれたものがありました。甲府市の大鎌田保育園のみんなが支援の畳の裏にそれぞれ書いてくれたメッセージ集が立てかけてあったのです。

疲れた身体に力がまた出るようなメッセージでした。

また、宇土市医師会の医師たちは毎朝早くの診療開始前の時間にミーティングを開いておられ、自らも被災されながら住民の方々の健康を気にかけられ、避難所に人々が戻る夜間の巡回を始めようとしておられました。私費を投じて炊き出しをされている医療機関もあると聞きました。行政の方々も疲れています。そのことを思い、ご自身たちでできることをされていらっしゃいました。私たちはDPATとして、現地の方々のがんばり過ぎやバーンナウトを気にかける立場なのですが、同じ職種として、先輩方の姿に感銘を受けました。かつて、阪神・淡路大震災のときに知り合わせてもらった、故・安克昌先生の師である中井久夫先生のご本の一節を思い出しました。
往診がすたれて行ったのには、さまざまな理由があろう。第一、昔は、医学、医療は医師の一身に具現しているようなものであった。その代り、肺炎患者一人を治したら一人前の医師とみられたものである。むろん、抗生物質以前の時代の肺炎治療のためには、医師は患者の家で徹夜する覚悟が必要だった。「冷やせ、あたためよ、辛子泥(からしでい)を塗れ、・・・・」その有効性はともかく、そういう医師の姿は、荒天を行く帆船の船長のように畏敬の念でみられたものであった。(中井久夫「治療の覚書」日本評論社、p212、1982)
私たちは災害の支援をさせていただくことで多くのことを学ばせていただきました。医療者としての自らの原点はなにか、人として生きるということはどういうことなのか。自らの経験から学んだことを次の人につないでいき、多くの方々の心の平安に貢献することで、災害にあわれ苦しんでいる方々、そして私より先にこの世を去ってしまった素晴らしい方々に報いていきたいと、強く思いました。

最後までお読みいただいた方、どうもありがとうございました。
-
前の記事
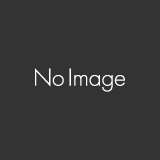
プシコ ナウティカ<終章> 2016.05.25
-
次の記事
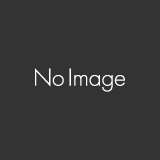
世界禁煙デー 2016.05.31