プシコ ナウティカ<終章>
- 2016.05.25
- 日記
今回はプシコ ナウティカの終章を読み終えて、忘備録的に感想を残すことにします。詳しい内容はぜひ本をお買いいただいてお読みいただきますようにお願いいたします。

松嶋健「プシコ ナウティカ」世界思想社
終章 生きているものたちのための場所
イタリアの歴史的な精神保健実践を見てきたとき、そこからは<地域>の決定的な重要性が浮かび上がってきました。問題は精神医療の中にあるのではなく、居心地の悪さは精神と身体を分離し、経験を個人的なものとして取り扱うやり方と関連があるとしています。医学の論理とは「自らの人生をどう生きるかについて自分自身の経験を用いて自分で決定することができない」ことの正当化であると筆者は看過しています。
地域に戻るとは、単に身体が病院の外で暮らしているということではなくて、人々と「一緒にいる」つながりの中に戻るということだと記されています。そして重要なのは、何かに介在されない(記号化されたり翻訳されたりしないことのように感じました)「直接」的な経験なのであるというバザーリアの言葉が参照されています。直接的な経験を音楽に例えていえば、それは音楽プレイヤーとヘッドホンによって供給される間接的なものではなく、セッションのような現実的な場なのであると記されています。
イタリアでは1980年代に「弱い思考」と呼ばれる風潮が生まれました。明証性(科学的なものもそうなのでしょうか)によって根拠づけられた知が現実を支配する強制力を持つ、これは医学が権力を有することを端的に説明するもので、これは「強い思考」すなわち「思考するもの」「されるもの」を分断する考え方ですが、行為の起点は「あいだ」にあるという「弱い思考」の立場では、ここでは「わたし」は強い主体性のある精神や意思のことではなく、多様なものや他人が交錯し出来事が生成してくるのを待ち、そして見守るような「わたし」だと考えられます。多くの支援の場面を経験してきましたが、個人的には「人との出会い/語り合い」の中でなにかが下りてきて個人の中に掘り下げられていく体験のことを思い出しました。
ここでもう一度、反精神医学のレインとバザーリアの施設についてのやり取りが紹介されれいます。”施設になんか構わず、施設から出て行けばいいと考えるレインに対して、バザーリアは、そうした考え方には落とし穴があるという。なぜなら、出ていくことのできる「外」があるうちはいいが、もはやそうした「外」がなくなったとき、すべてが施設化してしまうという問題が手つかずのまま残されてしまうから。”
人間が自由になるというのはどういうことなのか、筆者は再びこの話題に触れています。それは勝手気ままを無制限に行うことが自由なのではないとしています。それは全能妄想ににいたりつくだけで、そうではなく、人との関係性の中で相互的なリスペクトをもって経験を積んでいくことの重要性が再び強調されています。施設の中の障がい者向けの教育や訓練で人が育たないことをずばりと指摘しているような気がしました。
同時に「自己効力感」とは「やればできるさ」という経験の積み重ねである、という就労支援での重要なコンセプトについても触れてあり、リカバリー志向でない労働のことを「にせの労働」とばっさり切り捨てています。精神と身体は分離せずに人間が「生きている」とはどういうことなのか、イタリアの精神医療改革は「治療」から「生きることをどう支援していくのかに変わった」と記しています。
このような改革の中では、「権力」対「自由」のような二項対立図式で物事をとらえることはできないのは明らかだと筆者は言います。かつてのトリエステの病院の壁に書かれた「自由こそ治療的だ」の落書きも病院を廃止していく過程での自由と精神科病院廃止後の自由では意味が重なりながらも異なっているというのです。前者はいわば消極的自由に相当しますが後者は、積極的な自由を作り出す必要があり、しかもそれが権力の働きと見分けがつかなくなるという可能性が指摘されています。人々は完全に自由に行動しているが、同時のその行動の全体が導かれ統治されているという両義的な状況が生まれてくる可能性に言及しています。そして隔離型の施設が機能しなくなった後に、むき出しの暴力は行使されずに、地域における統治の技術を用いた「福祉的な管理の形式」が危惧されています。バザーリアは精神医学の技法が解放の道具としても抑圧の道具としても働くことをはっきりと認識していましたが、それが福祉施設での管理や自宅に戻さず病院の城下町化やグループホームとデイケア通所のセットのような、せまい範囲での選択のみが保障される選択の自由であったりするのではないでしょうか。イタリアでは生活は不便さがともなっています。自動化されない駅やマーケットなどは効率性を求めず、自らの行動が結果との因果関係を感じさせてくれるような体験を通じての自己制御が重視されているようです。生活の中で人や物事との生きた関係性を打ち立てるような行動をすることは心と身体の統一することに役立ち、効力感を通して主体性を手放さないこと、さらには「生きている度合いを高める」ために役立ちます。
人生には予測不能な事態やシステムが機能しない事態にあふれています。それらをどううまく機能させるかを考えるよりも、不便やエラーを別のものに作り変えていく技を磨いたほうがいいというように筆者は解釈しています、フーコーの師であった科学哲学者のカンギレムは「正常な状態」と「異常な状態」について、後者は正常性の欠如によって異常なのではなく、病的な状態もやはりある一つの生き方であると述べています。そこにある違いは「正常」と「病理」の間にではなく「健康」と「病理」の間にあると考えられ、生物の安定性が偶然の改造に対して開かれていなければより病気に近く、開かれていればより健康に近いと記されています。いわゆる脆弱性モデルの考えにに似てはいますが、脆弱性モデルと大きく違うのは、病的な状態を一つの在り方・生き方と考えているところだと思います。エラーをリスクとして回避し、人の行為の可能性を縮小しながら統治する生権力は、「誤ることができるようなもの」としての生命の力能を奪っていることにほかならない、としています。「リスクをとって行動する」権利についてはWRAPでも考えることの多い命題でもあり、胸のうちに落ちる思いがしました。
イタリアでは「近づいてみれば、誰一人まともな人はいない」という標語の書かれた標識が街中のあちこちにあることがそれらの理念を見える化していることなのだと思いました。そして、このように個人の特異性を容認し、可能にする入れ物としての社会についても考えている必要があります。あらかじめ確固とした個人と個人が集合体を形作っているのではなく、ずれを受け入れる集合体あってこその個人であり主体であると言えるような気がします。本には”イタリアの地域精神保健で実践されている<主体化>が、精神保健センターのスタッフだけでなく、地域の人々を巻き込んだかたちで追及されているのは、<主体化>というものが、常に<集合的主体化>だからである。”と書かれてありました。イタリアで<主体性>を病者に返還するために何より重視されているのが、生におけるこの集合性の次元で、人が<主体>を行使するためには、具体的で現実的な<集合性>の場所が必要であり、<地域>とはそうした<集合的主体化>の現働化の場所になっているとしています。真の権利擁護にはその手順に加えてそれらを生きたものにするための見えない大気や風のようなものとしての協働の理念が不可欠なのだとあらためて思いました。”侵犯したり、暴力をふるったり、対立しながらも、一緒に「そこにいる」ということ。現行の価値からするとネガティヴなものを否認したり、隔離したり、あるいは逆に同化しようとするのではなく、それでもそこに共にいるということ。それが、集合性の海に浸されているということであるし、地域精神保健の現場で「他者との出会いの必要性」と呼ばれていたものにほかならない”とこの本には記されていました。
私が出会ったメンタルヘルス関連の書籍の中でも、私に大きな影響を与えた書籍の一つでした。読み切って感じるのは、もう一度ページをめくりたくなるという想いとともに、「これを読んだあなたは、これからどうしますか」という問いかけのような気がしました。以前、上映会を開催したフランコ・バザーリアの伝記の映画化「むかしMattoの町があった」をまた見たくなりました。
http://180matto.jp/
最後までお読みいただいた方、どうもありがとうございました。
-
前の記事
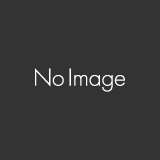
IPS援助付き雇用勉強会@5月のお知らせ 2016.05.22
-
次の記事
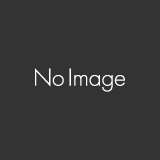
DPAT活動@熊本県宇土市で感じたこと 2016.05.27