プシコ ナウティカ<第6章>
- 2016.04.12
- 日記
今回はプシコ ナウティカ第6章を読み終えて、忘備録的に感想を残すことにします。詳しい内容はぜひ本をお買いいただいてお読みいただきますようにお願いいたします。

松嶋健「プシコ ナウティカ」世界思想社
第2部 イタリア精神保健のフィールド
第6章 <演劇実験室https://sumiyoshi-kaisei.jp/blog/wp/wp-content/uploads/と中動態
人間が人生の主人公となる活動の一つに演劇があります。芸術を通した世界との関係の再構築に意義があることがあるようです。ここでは精神保健センターの利用者によってのみ構成される劇団のプロジェクトが紹介されています。演劇に必要な2つの要素とは、観客と俳優の間の生の関係があること、演劇は自分自身の仮面を取り去り、人生の中で負わされた仮面から自分自身を解き放つためのものであること、だそうです。<演劇実験室https://sumiyoshi-kaisei.jp/blog/wp/wp-content/uploads/の活動は治療を直接の目的としない「演劇セラピー」ではなく、演劇そのものが目的です。精神障がいをも持つ人々のフットサル活動が、「運動療法」ではないことと似ている気がします。そして医療の倫理を排除すること、精神医療の非関与の原則が紹介されています。また、劇団を作るのも最終目的ではなく、一つのプロセスだとされています。それはリカバリーの道のりに似ている気がしました。そして責任者はこのプロジェクトが気晴らしでも援助や娯楽の仕事ではないと明言し、スピリチュアルなものを追及しているとし、このため医療関係者は見学が許されていませんでした。
精神医療の非関与については、一部の精神科医から抵抗がありました。医療の枠組みから外へ開いていくことを希求しても、未知のものに対する恐れがしり込みを産み、そのチャレンジが止まってしまうことは「施設化」になるのではないかということです。サヴェリオ医師の言葉は本当に現実的なものでした。
「われわれは精神病院の扉を開放することができた。けれでも、そこから去るか、去らないかは、その人次第なんだよ。扉が開いているか閉まっているかという問題ではないんだ。大勢の人たちが中にとどまるんだ、扉は開いているのに。怖れがあるんだよ。」
ここには、この著作の本質的なテーマでもある「自由な主体」とはなにか、がまた問われています。ある日突然人は「自由な主体」を手にするわけではなく、主体と客体のあいだに明確な分割線は引けず、この<演劇実験室https://sumiyoshi-kaisei.jp/blog/wp/wp-content/uploads/はこの「あいだ」を発見し探索する場であるとしています。利用者の多くはプロの俳優になろうとする動機からではなく、担当のオペラトーレ(ヘルパーのような存在)から提案があったり、少し興味がある、という理由で参加した人たちでした。
実際には、演劇活動には普通の演劇者が行うようなハードさのあるトレーニングが行われました。<演劇実験室https://sumiyoshi-kaisei.jp/blog/wp/wp-content/uploads/には本人が主体的に参与することが求められ、時間を守ることが主体性を示すための第一のステップとされていました。つまり、「普通」の演劇者が求められることの一つが求められていたのです。最初のトレーニングはゆっくりと意識しながら歩くことで、これはマインドフルネスの方法の一つに似ている気がしました。その後もさまざまなトレーニングが「紹介されていますが、コミュニケーションしようという意思なしにコミュニケートでき、表現しようとする意思なしに表現できる環境を感じ取ることができるようになると書かれています。そしてフットボールの選手がフィールド全体をあたかも自分の身体の延長のように感じ、それゆえ、パスを出す方向を見なくても、的確にパスを出せるときの感覚に近いとしています。このように環境への働きかけと、環境との対話を通した一体化が許される環境が重要なのだと筆者は論じています。そして「自分の中から何一つイメージがわいてこないときでも、彼らが私のプロセスを起動する」という参加者の言葉に、リカバリーの道のりで一番たいせつなものが希望である、というフレーズを思い起こしました。
筆者が実際に<演劇実験室>の参加を通して学んだものは「強い主体であろうとすることの病い」と呼べると書いてあります。主体か客体か、能動か受動か、という白黒の二元論ではなく、その間にある閾(しきい)に向かって自己を開き、具体的にその領域を探索していくための道具として<演劇実験室>はあったと言えるとしています。モニカはかつて「強い主体」の信奉者であったが、その精神的不調は「強い主体」としてあろうとしていたところに由来していた、と振り返る場面は、納得のいく気がしました。そして身体による「自由連想」によって、人生の身体的履歴が早送りで再生されるような、あるいはまたいつもの自動的な行動パターンが出てくるのだとしています。そしてこの精神の枠(または鎧)のようなものを外していくことは、<演劇実験室>のメンバーは「プシコナウティカ」と呼んでいたそうです。これは「魂の航海」という意味だということです。自分をいったん壊して、さらに懐の深いものに再統合していくためには、安心してそれに集中できる環境が必要だとされ、そして参加者のみが立ち入れる空間がそれを可能にするとしています。
そして参加者のそれぞれの体験が語られ、その共通したものは能動と受動の間の微妙な位相があるということを経験することになります。それが中動態と呼ばれる文法上の表現だそうです。ここで言語論的な考察もありますが、チュ動態は無主語文になり、「行為者の不在、自然の勢いの表現」であり、私は、ではななく言外にある「われわれ」の次元の二重性を同時に生きることに他ならないと筆者は記しました。
「強い主体」というある種の幻想から解放されることの重要性、社会的規範を絶対視しないでふるまい、生きることの必要性がこの章から私が強く感じ取ったことです。現実の世界は不確実なもの、予期できない者に対する許容度は著しく低くなっていて、物事がそれ自体の生成の論理と時間にしたがって性施してくるのを辛抱強く待つことやそれを自分自身が観ることが難しくなっていると思われます。私の職場の先輩は、私が余裕をなくしているときに「待つのだ」とアドバイスをくれたことがあり、そのことをもう一度胸の奥から取り出し、眺めて、しまうような気がしながら読みました。
最後までお読みいただいた方、どうもありがとうございました。
-
前の記事
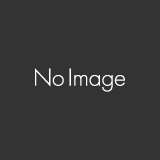
IPS援助付き雇用勉強会のお知らせ@4月 2016.04.11
-
次の記事
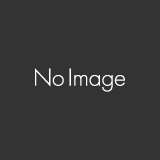
よんもくWRAP@4月のお知らせ 2016.04.14