プシコ ナウティカ<第2章>
- 2016.03.27
- 日記
今回はプシコ ナウティカ第2章を読み終えて、忘備録的に感想を残すことにしています。

松嶋健「プシコ ナウティカ」世界思想社
第1部 イタリア精神医療の歴史と思想
第2章 フランコ・バザーリアの思想とその実践
イタリアの精神医療改革は1か所から起こったわけではありませんでしたが、この章ではイタリアの精神科病院廃絶の最大の功労者とされるフランコ・バザーリアの人生を振り返りながら、実践の背景にあった一つの思想を取り出そうとしています。
バザーリア15歳のころに第二次世界大戦がはじまりました。大戦中に医学部に入学したバザーリアでしたがレジスタンス活動に加わって逮捕投獄されました。バザーリアは現象学に親しんでおり、ビンスワンガーの現存在分析を通して疾病を了解することを志向していました。病者の主観的体験としての病を説明ではなく了解するためには、観察者である医師自身が病者の前に存在して、内側に何かを触発し引き起こすという位置に立つことになります。そのときには主体vs客体や観察者と対象者、といった関係性の分断は崩れ「わたしたち」だけが存在することになるのです。
これは最近、私たちの間で感じている「当事者vs専門職」とか「病院vs地域」といった二分法に対するもやもや感を解消して売れる概念だと感じました。
バザーリアは自らの論文において、「症状」を「状況」として捉えなおすことを提唱し、その「状況」は単に説明されるだけでなく了解されるべきものだとしました。彼は大学病院での13年間の経験を経た後にゴリツィアの精神病院院長になりました。この時には、精神病院では「卑小な精神科医」たち(よそには職を見つけられなかった連中、というのも精神病院というのは安全、保護、監視を提供する場所であって、〔そこで働く医師には〕特別な収れんは必要なかったから)がいると考えていました。院長としてゴリツィア病院に到着し、彼の見たものは、収容所の非人間的な環境における被収容者の自然な反応が治療スタッフに対する嫌がらせ、もしくは病理の現れとみる固定化された見方に支配された場所でした。彼は拘束を開放し、閉鎖病棟を開放することから始め、最初は小さなことから徐々に入院者のそれぞれを一人の人として扱い、権力を持つ者が人から奪った権利を返していきました。これはエンパワメント-平等で公平な環境により人間の能力がありのままに発揮できるようにすることーの思想につながるものであり、ほかに移されていた権限を戻すことともつながっているという含意が心に浮かびました。
筆者はここで精神病院という施設が、医学の名のもとに全制的施設として正当化され、治療の技術とされていたものが人間をモノとするための技術の一つとしてとらえられるということを指摘しました。ゴリツィア病院内に治療共同体の概念が導入され、集団討論「アッセンブリア」とミーティング「リウニオーネ」が始まり、同時に病院は社会へ開かれていきました。問題は精神病院の中だけではなく外にある。つまり施設もさることながら、それを必要とし維持することを可能にしている社会-排除された者の包摂に関心を示さない-に目を向けなくてはならない、精神科における反施設・脱施設化の運動は社会の中で精神医療が担っている機能についての問い続けることが必要になってきます。精神病院を破壊することはそれ自体が目的なのではなく、そのことで社会を治すことを試みたのだと筆者は考えています。
改革の途中で、入院患者の一人が外出中に元妻を殺してしまうという「事故」がありました。バザーリアの考えに反発する人々の非難は勢いを増しました。そこでもバザーリアは社会は精神病者の「危険性」を言い立てて管理や監視の強化を徹底するようにと要求するのに対して、本当の問題は「病気」にあるのではないと応えました。結局、事故の年の秋にバザーリアはゴリツィアを去りましたが、その後バザーリアはアメリカにわたりました。
アメリカでは脱施設化が起こっていましたが、地域精神医療の貧困から慢性患者は公立病院からナーシングホームに「移動」しただけであり、かつまた退院者は回転ドアに陥ったり、司法施設に収容されたりしていました。それを批判的に見た彼は精神病院を温存せず解体しなければならないと確信したようです。イタリアに戻ったバザーリアは1970年にコロルノ病院の院長に任命され、同時にパルマ大学精神衛生講座も受け持つようになりましたが、ここでも行政は「良き精神病院」より先には進もうとせず、またしもバザーリアは病院を去ることになりました。そして1971年、バザーリアはトリエステの県立サン・ジョバンニ精神病院に赴任したのです。
直接患者を診察することはなくなっていたバザーリアですが、彼は、彼の治療方針に懐疑的なスタッフから信頼を勝ち得るために、長く拘束を受けていた「最も難しい」患者を担当しました。長く話し合い、最終的にバザーリアは彼の病院のカフェの運営を任せるスタッフとなるまでにサポートしたのでした。このような「重い」人々の回復の過程を目の当たりにし、そして責任を持つ仕事をする仲間として一緒に働くようになっていくことの重要性を私は心の底から支持します。
さらに退院したが外に居住先のない人々が病院内に居住できる「オスピテ(客)」というステイタスを作リ出しました。オスピテは精神病院に自由に出入りできるので、これまで存在していた精神病院の内と外、精神病者と健常者の明確な分割を撹乱しました。トリエステでのこの境界的存在は、施設の外と内の双方で矛盾を生み出したのです。市民との交流が進み、アパートを共同住居として住む人たちが出てきました。そして、「病気」があるのではなく、代わって一つの「危機」の表現であると考えることが強調されるようになりました。問題を危機とみるのか、それとも診断とみるのかは別のことで、診断・症状は客体的なものであるのに対して「危機」は主体性ないし関係性の問題だと思われます。
バザーリアのいう「生の危機」とは、生きていくなかで誰でも起こりうるような危機のことで、それが客観的に「病気」であるかどうかは主要な問題ではないとされます。それはWRAP(元気回復行動プラン)でいう「クライシス」に相当するもののように思われます。
「病気を括弧に入れる」ことの必要性をバザーリアは強調していました。彼は精神疾患が存在しないということを主張しているのではなく、人間的状況としての狂気があることを認めています。病気は社会性の文脈の中で規定されており、人が危機的状況あるとき、そのことにどのように向かい合うかというのが精神科医に求められているのだといいます。
資本主義において「病気」と「非生産性」は結びついており、精神科医は社会から「”非生産性”と烙印された人々の一部(社会的危険性のある人々)を管理することに他ならない、と著者はまとめています。そして精神病院は「医学のイデオロギー」によって、監獄よりも無際限の暴力の行使が許されることになります。これはかつて「らい予防法」下の療養所でも苛烈な制限を療養所長の権限一つで決定されていたことが思い起こされます。
もう一つ、トリエステで強調されたのは「労働者になる」ということでした。閉鎖された精神病院の病棟で職業研修のコースがいくつも行われ、「病者」のアイデンティティから社会協同組合で働くことになるような仕組みができあがりました。社会協同組合はA型とB型があり、A型は組合員以外の利用者に対し、B型は「社会的に不利な立場の人々の就労」を目指すものでした。いずれも「本当の仕事」であり、定義は若干異なりますが、IPS援助付き雇用がめざしている「仕事」やクラブハウスの目指す活動に通じていると思います。
1977年にサン・ジョバンニ精神病院の閉鎖が宣言されました。結局その年のうちには閉鎖はならず、翌年法180号が成立しました。この本の147-148ページの一節と、その後の反精神医学の旗手レインとバザーリアの対談は、精神病院の外からでなく内部にありながら、脱施設化や脱制度化の端緒を担おうとする、病院スタッフに対するメッセージとして元気の出るものでした。
諸々の矛盾を開きつつ、他者とともにそこにいる、ということ、これが「矛盾を生きること」とバザーリアは表現しました。そして、病院がなくなって地域に出ても、制度を問い直し、矛盾を開き続けることなければ、その出た場所が新たな施設になる危険性が常にあるとバザーリアは危惧していました。「地域課という基準が有力になり、古い状況が一見新しい状況に変容したように見える。だがそこは常に、福祉的な管理の形式を再び持ち出す危険性が伴っている」。
1980年にバザーリアはなくなりました。「やればできる」ことを身をもって示した人でした。そしてやり続けることの必要性も示唆し続けた人でした。
最後までお読みいただいた方、どうもありがとうございました。
-
前の記事
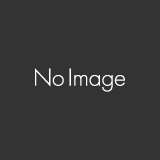
精神医療国家賠償請求訴訟研究会 2016.03.26
-
次の記事
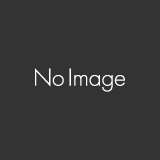
プシコ ナウティカ<第3章> 2016.03.30