激励禁忌神話の終焉
- 2014.02.06
- 日記

井原裕著「激励禁忌神話の終焉」日本評論社
うつ病に励ましはタブーなのか?
精神科の治療に薬は必要なのか?
精神科医療の常識をくつがえす!
となかなか刺激的な帯が目立っている関係者必読の書です。「こころの科学」に連載されたものをまとめたというこの本の内容は多彩です。
そもそも「うつ病患者を励ましてはならない」というのは国家試験にひとつの問題があるのだと書いてあります。つまり、医師国家試験問題の精神科に関する場面で選択禁忌肢(やってはならないこと=その回答をすると、他の問題ができていても合格判定をもらえないという)であるのは
・うつ病におけるレセルピンの使用
・非指定医による医療保護入院
・慢性統合失調者に対する精神分析療法
・うつ病に激励
となっています。
もちろん激励してはならない時期があることも事実なのですが、適切であたたかい励ましは必要であることも多いとされています。海外の教科書などでは激励は禁忌にはなっていないわけですが、この問題が有名になってしまい、精神科以外の医師に広くいきわたり、さらに独り歩きして一般の方々に信じられているのではないかというニュアンスになっています。古典的なうつ病・メランコリー親和型の場合にはそれはあてはまることが少なからずあると思いますが、たとえば認知行動療法の場面では激励とみえるような介入は随必要となるでしょうし、就労支援の場面でもちょっと肩を押したり、励ますという場面もでてきているような気がします。それらは「うつ病には禁忌である」ということになっているわけではないと思います。
もちろん、すべての方を激励していいということではなく、あとがきで著者は「オールオアナッシングでとらえるなかれ」「無鉄砲に激励することではない」と書いています。それぞれの人の状況を専門医が判断してとる態度の一つとして激励を選択肢の一つにそなえていることは悪くないと思います。
また、精神科臨床で薬物療法に偏らず、精神療法の場面を大切にするという、著者の姿勢が随所で見られますが、精神科医と患者さまの関係は人間対人間の関係のようではあるものの、均衡を欠いた関係である、ということに注意を喚起されています。精神科医は白衣を着て決して素顔を見せず患者の内面を見、患者さまは普段口にしないことも安心して口にするのだと書かれてあります。したがって、精神科医は好事家的関心に身を任せて、面接本来の目的を逸脱するようなことがあってはならない、と戒めてあります。関心を寄せるというのは人を元気に保つために重要なファクターでもありますが、それはあくまで、今はまだ苦しんでおられる方の回復に向けてであり、自分の個人的興味を満足させるものではないということだと考えました。
第6章では、わが国の国民皆健康保険制においては、保険の範囲内でどうしても短時間で面接をしなくてはならない場面が多く、いきなり「どうですか」から始まるのでは芸がない、と書かれています。面接では精神科医は「薬のソムリエ」となって薬についての感想を尋ねるのではなく、前回面接のさいのテーマを続けていくことが必要で、無難な言葉から診察に入るのではなく、短時間で何を見抜き、どう解決していくか、に焦点を当てることが重要という指摘と思いました。
臨床に携わる多くの方々にとり、読んでおくべき1冊と思いました。
最後までお読みいただいた方、どうもありがとうございました。
-
前の記事
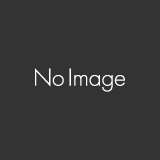
みんなのまつり2014開催のお知らせ 2014.02.04
-
次の記事
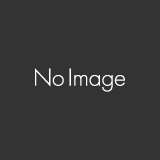
回復するのに締め切りはありません 2014.02.08