Competitive employment
- 2011.02.02
- 日記
就労支援の成果として価値を与えられている”competitive employment”。日本語では「競争的雇用」ということになります。アメリカでは職業に対する機会均等性が強調されているため、リハビリテーション法における援助付き雇用の定義では、障害のある人が働く場が「フルタイムあるいはパートタイムの仕事で、平均週20時間以上の労働」であること=競争的雇用を目指すことが援助付き雇用に必要とされていました。
日本では「一般就労」という考え方があり、福祉工場での保護的雇用や授産施設等における福祉的就労と対比した、企業や官公庁等での通常雇用をさしています。ただ、この「一般就労」には特例子会社や重度障害者多数雇用事業所のような事業所での就労が含まれています。また、「福祉計画」における「一般就労」とは「在宅就労者を含む”雇用契約を結んだ者”と自ら起業した者」になっています。
IPS援助付き雇用においては、”competiitve employment”は
・労働マーケットにある「一般的な」仕事
・最低賃金以上の収入
・通常業務で、健常者と同じ職場であること
・精神障がい者用に用意された仕事ではない
・仕事は個別に用意される
・健常者も利用する一時的な機関から紹介される仕事と、季節的な仕事は含まれる
Blyler,CR:Defining Evidence-Based Supported Employment.SAMHSA Center for Mental Health Services,2008
ということになっているようです。週20時間以上の労働、というしばりがない研究もあり、「1日以上働いた」で「就労群」にカウントされているものもあるようです。
IPS援助付き雇用の有効性について考えたるとき、どういったアウトカムを「有効」としているのかについて考えてみることが自らの実践を振り返る際に必要なのかもしれないと思いました。
最後までお読みいただいた方、どうもありがとうございました。
-
前の記事
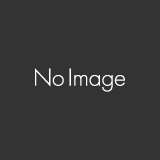
日本代表、四度アジアを制す 2011.01.29
-
次の記事
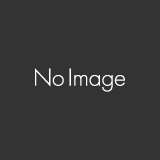
自殺防止のための電話相談技能研修 2011.02.07