死を思うあなたへ
- 2017.10.11
- 日記
話題の一冊を読みました。幼いころから家庭の問題で苦しみ、思春期のの大半を精神科病院で過ごした後、現在は新しい家庭を築いて家事や育児のかたわらで、行き場のない犬や猫が永続的に安心して暮らせる家庭をみつける「動物の生きる権利を守る活動」をしておられる方の経験に基づくストーリーです。

吉田ルカ著「死を思うあなたへ-つながる命の物語」日本評論社
著者の方が生育したのはいわゆる「エリート」の家庭のようでいてDVをふるう独裁的な父、それを止めようとせず暴力の前に無力である母。著者の方はいつも「悪いのはあなた」と言われてきたのです。そのような生育環境において自分に対する評価は常に低くもたされ、信頼できる大人にも出会うことがなく、家にも居場所がなく、著者の方は高校3年になって精神科の門をくぐったとあります。
19歳になる前日、睡眠薬を大量に服用しての自殺企図から目覚めると、著者の方は精神科病院の狭い個室のベッドの上に寝かされていました。精神科病院では様々な「患者さん」同士の触れ合いがありましたが、ここには描かれていない、それを凌駕する現実があったかもしれません。感情の起伏なども精神科医の処方によって先鋭化してしまったこともあったかもしれません。
著者の方が精神科で知り合った人々のうち、自殺された方もおられたとありますが、著者の方は大学病院で何人かの信頼できる精神科の医師に出会ったことをきっかけにリカバリーの道を歩んでいかれました。本からは回復とは、それまでの苦労を乗り越えたり、苦労がなかったことにすることではない、ということが伝わってきました。著者の方によりそってくれた精神科医の人たちは病より人を診るという、ある意味当たり前の診療をしているようにみえますが、現実の精神科病院はそんなものではない、と本書の前書きにおけるある精神科医の指摘は重要だとも思います。ハンセン氏病をお持ちの方に対するのと同じような国の施策によって方向づけられ、差別的な人員配置を認める法体系化において、ある意味精神科病院は社会の構造によって存在が決められてきた面があるからです。そういった状況のもとにおける精神医療の質の格差、つまり出会えた精神科医の質の差が「運」によっており、そのことで人生が大きく左右されることは悲しいことだと思います。
あるシーンがとても心に残りました。
「なんで死んだらあかんの」
「ワシがかなしいからじゃ」
「そんなん知らん。それは先生のエゴや」
その時は著者には、担当医個人のエゴにしか映らなかったのは本当でしょう。でも、この本を読んで、病いを持つ人を人として受け止め、医療という関係性の中で「わたし」と「あなた」をへだてない関係性の中で自分の責任をはっきりとすることついて、忘れてきたものをもう一度思い出した人が少なくないでしょう。一つ一つの会話はそれだけでなく、つながりの中で細い糸が次第に太く紡がれていったり、あるいはまたその場の会話から自分自身との対話がおこって新しいものに出会うこともあるでしょう。そして、医師とのかかわりがすべてではなく、人は人によって癒され、そして誰しもが成長するものであることを信じてよいことをあらためて感じたかもしれません。私は、本書を通して自分の来し方と対話し、出会った多くの人たちとの対話がよみがえって深い感情が生じるのを感じました。
そして私は、かつて下記の本を読んだときと同じような、心の回復の旅路の物語に触れて、また一つ、人の持つ力というものを学んだ気がします。
最後までお読みいただいた方、どうもありがとうございました。
-
前の記事
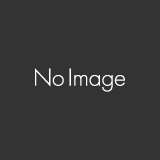
ご家族のつどい@9月のお知らせ 2017.09.22
-
次の記事
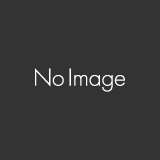
IPS援助つき雇用勉強会@10月のお知らせ 2017.10.12